☆ 初代肥前国忠吉 ☆ 『特別貴重刀剣』 新刀最上作にして最上大業物 寒山鞘書 收藏
一口价: 2500000 (合 127000.00 人民币)
拍卖号:f1066016957
开始时间:02/11/2025 13:02:10
个 数:1
结束时间:02/18/2025 23:02:09
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
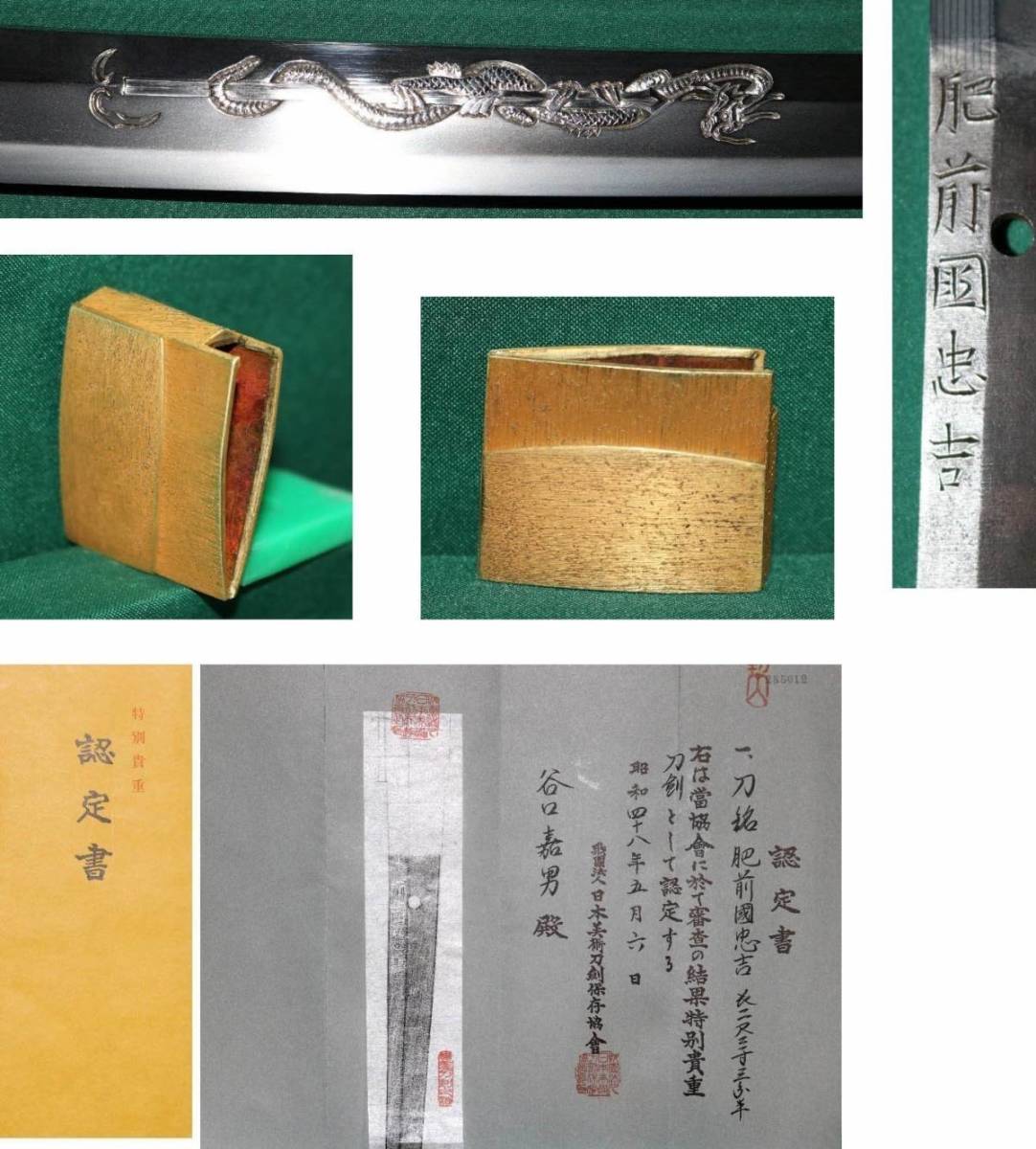



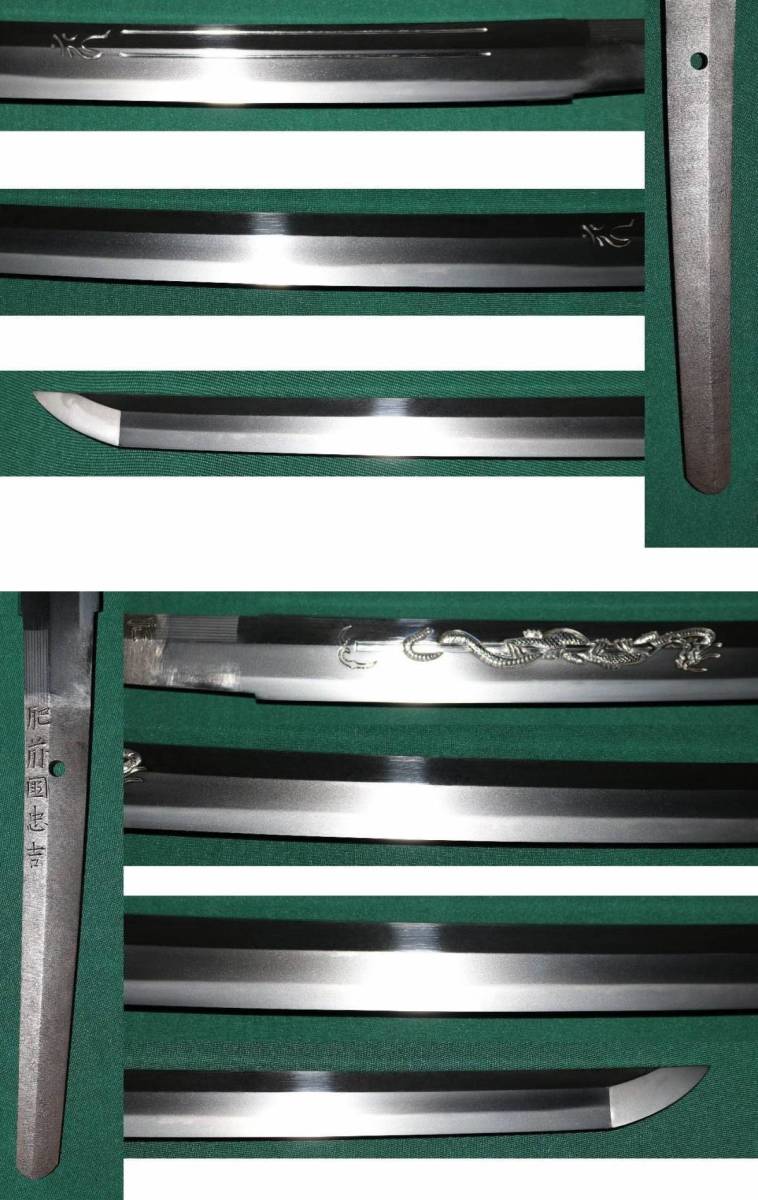


xvpbvx |
| 長さ 70.7㎝ | |
| 反り 1.8㎝ | |
| 元幅 約3.15㎝ | |
| 元重 約6.7㎜ | |
| 先幅 約2.2㎝ | |
| 先重 5.0㎜ |
xvpbvx |
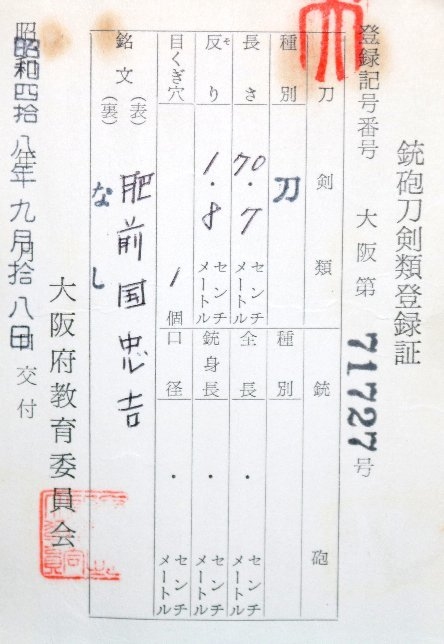

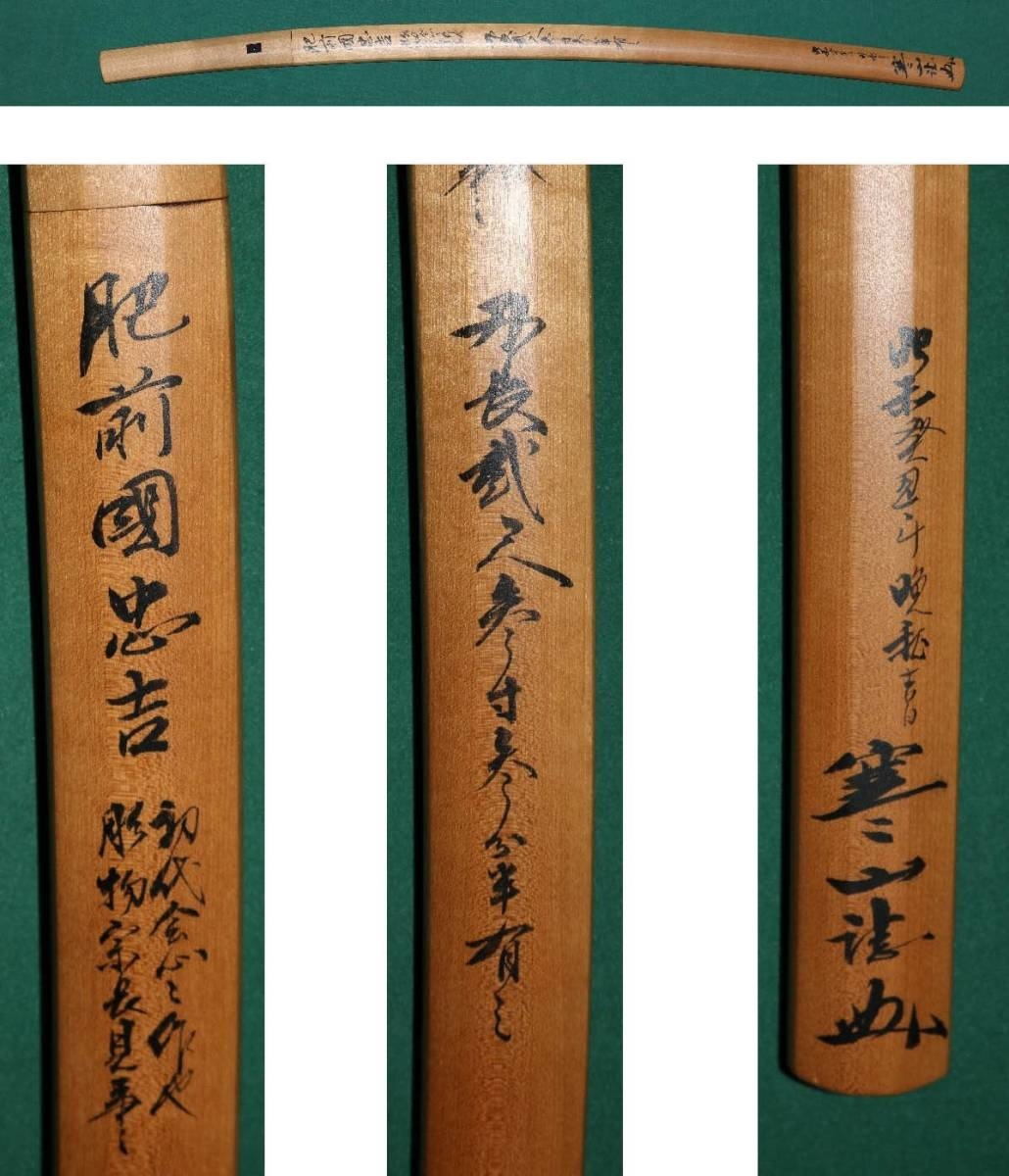
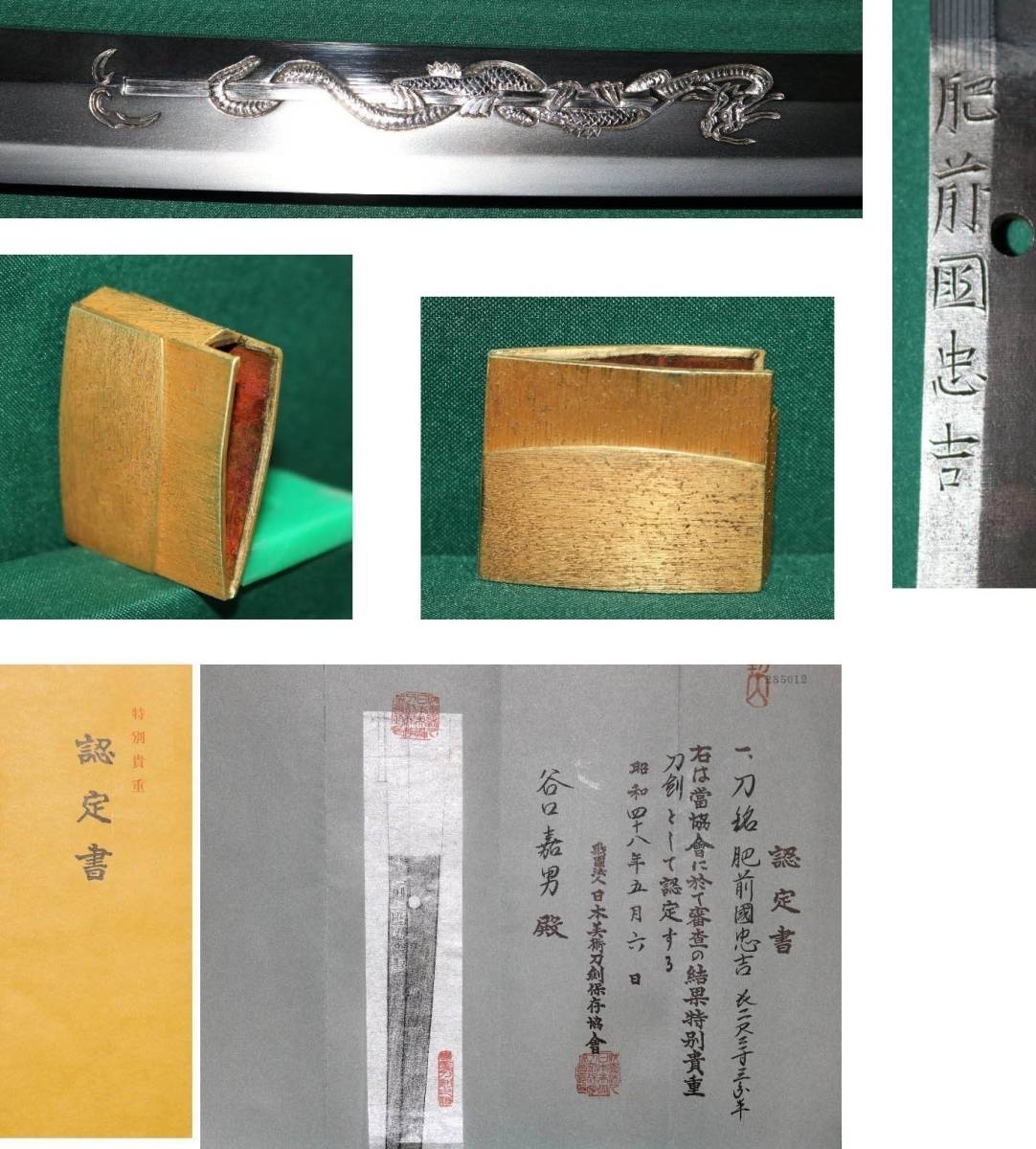



| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐