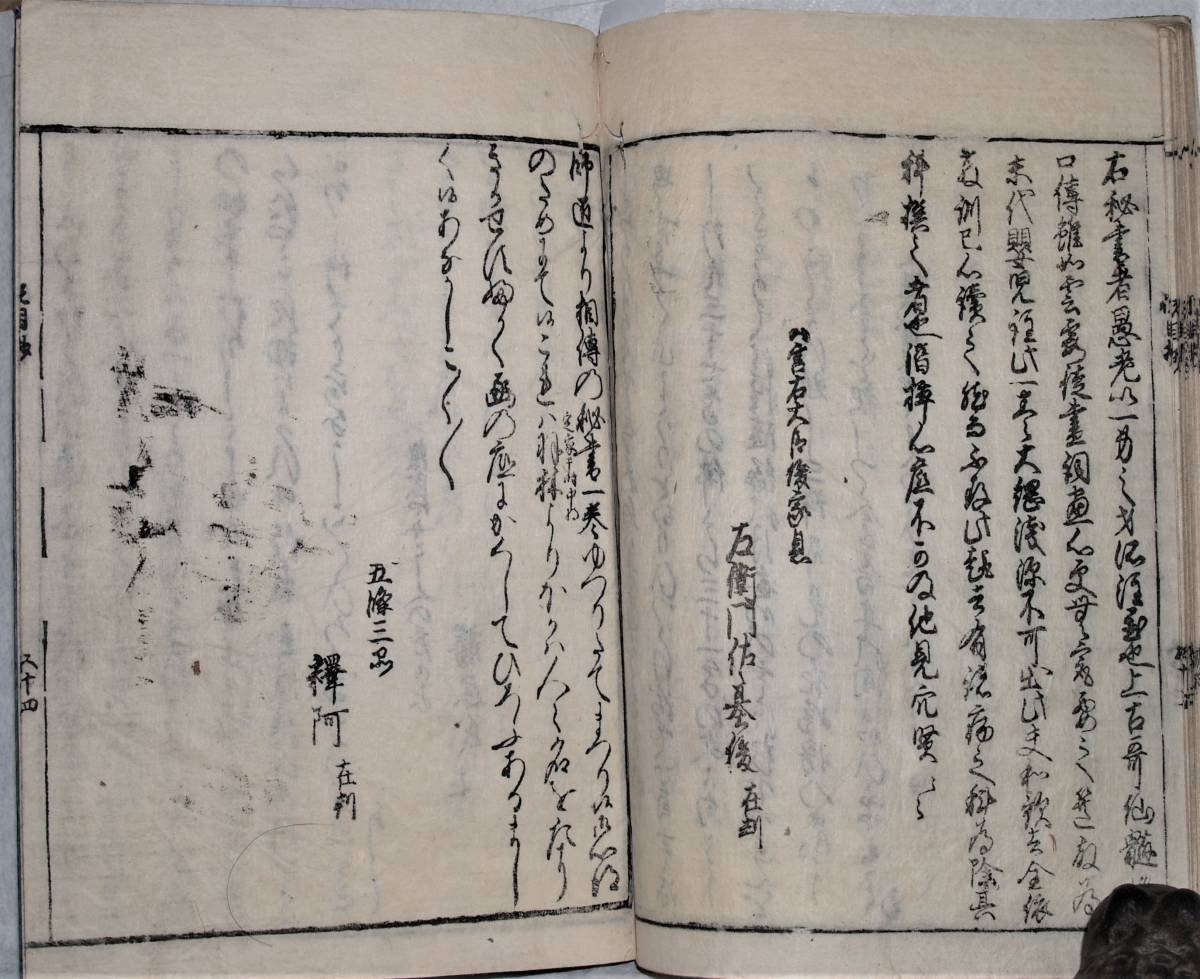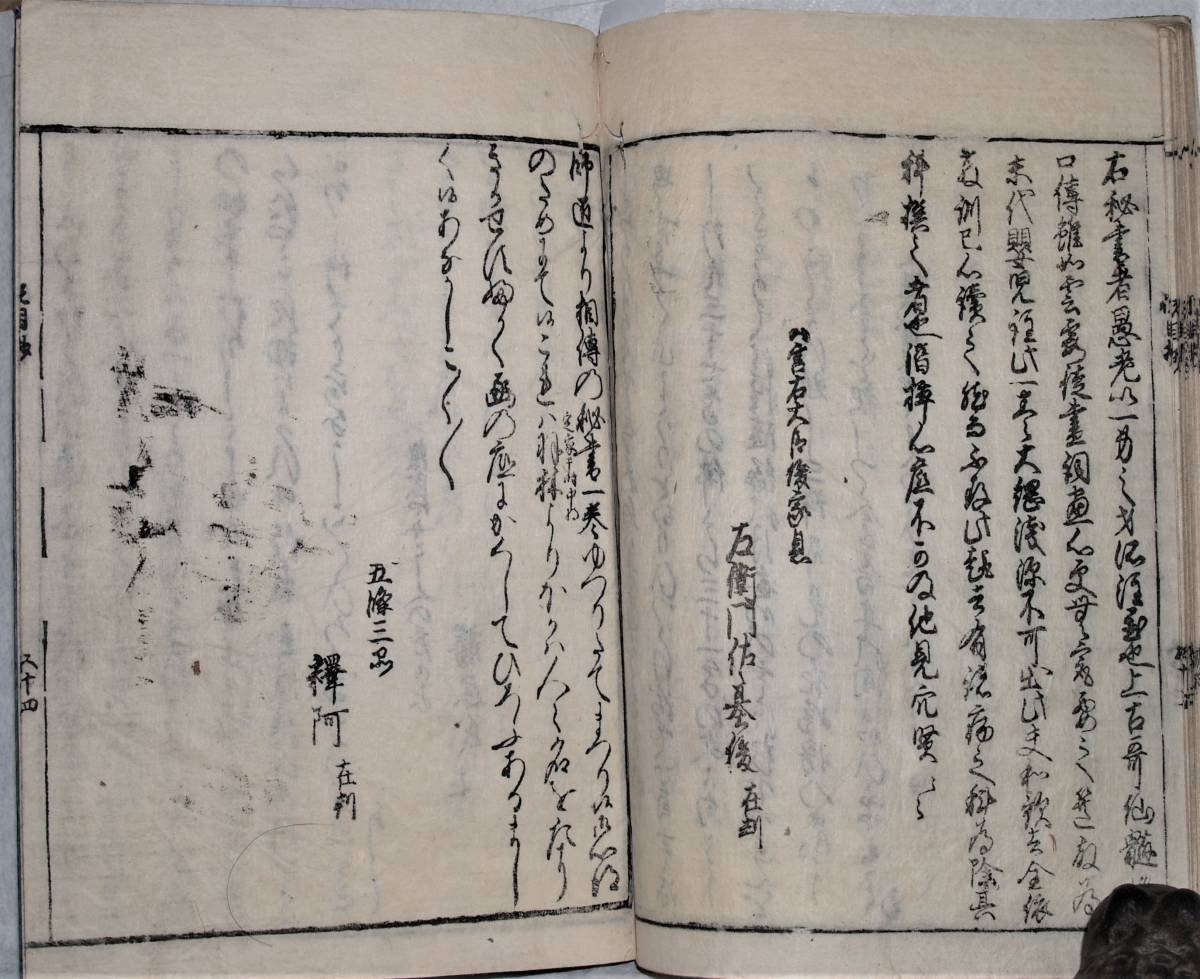


27×18.2cm
全55丁 半丁 11行
【内容 群書類従所蔵本(表記もこれに倣う)を底本とした項目】
・二本とも、項目毎に、文頭に漢数字の「一」が付いているのが基本だが、 どちらか一方に付いていれば、他方もそれに倣った。
・一本が項目として立てていれば、他本もそれに倣った。
・板→出品本・群→群書類従本
・丁付けは板本(出品本)に依る
01 物をかなにかくべきやう 2丁表
02 大方かきたがへて 2丁裏
03 歌をくゝりよむ事 3丁表
04 うたをよまんには 3丁裏
05 歌はすべて 4丁表
06 和歌の式には 4丁裏
07 ふるき歌の第一二句をとりて 6丁表
08 題をよく心うべきやう 7丁表
09 深雪などいふ題をえて 8丁裏
10 立春しいはん題に 9丁表
11 歌をよまん時【板に無し】
12 其物のすぐによまれぬには 10丁表
13 歌をかならず上の句より 10丁裏
14 歌をば百首千首万首【群と語句が異なる】 11丁表
15 歌の冥加をおもはゞ
16 題を書様は 11丁裏
17 歌に善悪あり【板に項目としては立てず】
18 歌は人によりて讀かゆべし 12丁表
19 叉縁の字をこしにすへずして 13丁表
20 かなをいたはるといふは 13丁裏
21 假名をえるといふは 14丁表
22 異名を心得よとは
23 たすけ字を存せよといふは
24 やすめの字といふを 14丁裏
25 かなをあまさずと云は 15丁表
26 心をあまさずといふは
27 詞の上下をせざれといふは 15丁裏
28 縁の字をとをのけずと云は
29 うへ下を心得よといふは 16丁表
30 これもおなじ心の歌なり 17丁表
31 前にも申侍ど 17丁裏
32 好みて可讀文字七あり 18丁表
33 忠峯、忠見はともに 18丁裏
34 棟梁は、も文字
35 康秀は、よ文字を句の下に 19丁表
36 遍昭。素性、共にの文字を句の下に
37 中のきみは、や文字を句の下にをきて 19丁裏
38 友則は、み文字句の下に有て
39 ある口傳に云 20丁表
40 やすめの字とて二字あり 20丁裏
41 阿倍清行が式目
42 公任卿抄云 21丁表
43 病をさるべき事 22丁表
44 同心は、詞かはりて 22丁裏
45 亂思は、第一の初の一字
46 欄蝶は、初の5文字の終の字
47 渚鴻は、第三句の終の一字 23丁表
48 花橘は、名物題をかくす事也
49 老楓は、題をよみはやさぬ事也
50 中鈍は、五もじを故六字になし 23丁表
51 後悔は、心も詞も同じ事ながら
52 歌に詞の病とて 24丁表
53 かしがましき字とて【板に無し】
54 五下のりんとう、五上のりんとう 25丁表
~~半丁分白紙~~
55 万葉集に、さうもん歌といふは 26丁表
56 歌に、あまたの躰あり 27丁表
57 長歌とは、皆人、すゞろに句あまりて長を申
58 旋頭歌といふ物あり 29丁表
59 混本歌といふ物あり 30丁表
60 折句の歌といふものあり 30丁裏
61 くつかぶりの折句といふ物あり 31丁表
62 をみなへし、花すゝきといへることを
63 叉初の一字と終の一字とを 31丁裏
64 廻文とは、かしらよりも、しもよりも 32丁表
65 かくし題とは、むねといふべきことをば 33丁表
66 疊句といふ事有 33丁裏
67 俳諧
68 答、これは歌を返すをいふ也
69 小町がもとへ、素せいほうしが 34丁表
70 業平が家に侍ける女に、俊ゆき
71 大弐三位さとにいで侍けるを 34丁裏
72 叉あふむがへしといふ物有【群に項目としては立てず】 35丁表
73 古歌をとる事、第一の大事也 36丁裏
74 歌に、大事有、てにをはしいふ事あり 39丁裏
75 ことに禁忌をさるべし、歌合ならぬには少しの難はとがならず 40丁表
76 はゞかるべき名所并詞 41丁裏
77 岩代の松は、事のおこり憚りあり 42丁表
78 夜のみじかきといふ事 42丁裏
79 我述懐とあらはにみえたる歌なり 43丁表
80 堀川院の中宮に、
81 抑うつぶし染、つるばみ、しゐ柴、 43丁裏
82 歌合ならぬには、題をみなつくす事は
83 歌を眼、耳、鼻、舌、身、意にあてゝ 44丁裏
84 和歌は、我朝の風俗なれば 45丁表
85 叉人に一度の過あればとて 46丁裏
86 大かた、何事にも名を得たる人は 47丁表
87 叉其ふるまひ、心ばへ優なるべし【板に項目としては立てず】
88 俊賴朝臣かたりて云【板に無し】
89 ある殿上人、みな月の廿日あまのり比 48丁表
90 野宮の歌合の判者は、源順也 50丁表
91 大中臣能宣が 51丁表
92 末座としてよき歌なればとて【板に項目としては立てず】 51丁裏
~~改丁~~
93 抑和歌に前後の二句あり【群に項目としては立てず】52丁裏~52丁表
奥書・刊記 53丁裏~55丁裏
大宮右大臣俊家息 左衞門佐基俊 在判
五條三品 釋阿 在判
俊成卿女こしへの尼御前 藤原氏 在(判)
(妙阿 在判 ←群書類従本にあり)
起請文のこと 為氏 在判
正安元(1299)年二月十七日 前大納言為世 在判
正保弐(1645)乙酉五月吉日 板行
【因みに】
『悦目抄』は藤原基俊作と言われているが、実は偽作。成立は鎌倉中期とされるが定ではない。
勿論、世に出てからずっーと「基俊作」と信じられていた(はず?)。
【参考】『悦目抄』 【デジタル大辞泉】に依る。
歌論書。2巻。藤原基俊著といわれるが偽作。成立年代は鎌倉中期とされるが未詳。
和歌の作り方・仮名遣い、先人の作風などについて述べたもの。『更科記(さらしなき)』。『和歌一流』『和良日久佐(わらひくさ)』とも称される。
※全体的に、経年によるくすみ、汚れ、若干の虫食いあり。
※袋とじの部分に、銀杏の葉が何枚か挿入されている。恐らく、「栞」に使ったものと思われる。現代の本のように挟んでおくと、ページを開いた拍子にハラハラと舞ってしまう可能性がある。上手く考えたものだ。