








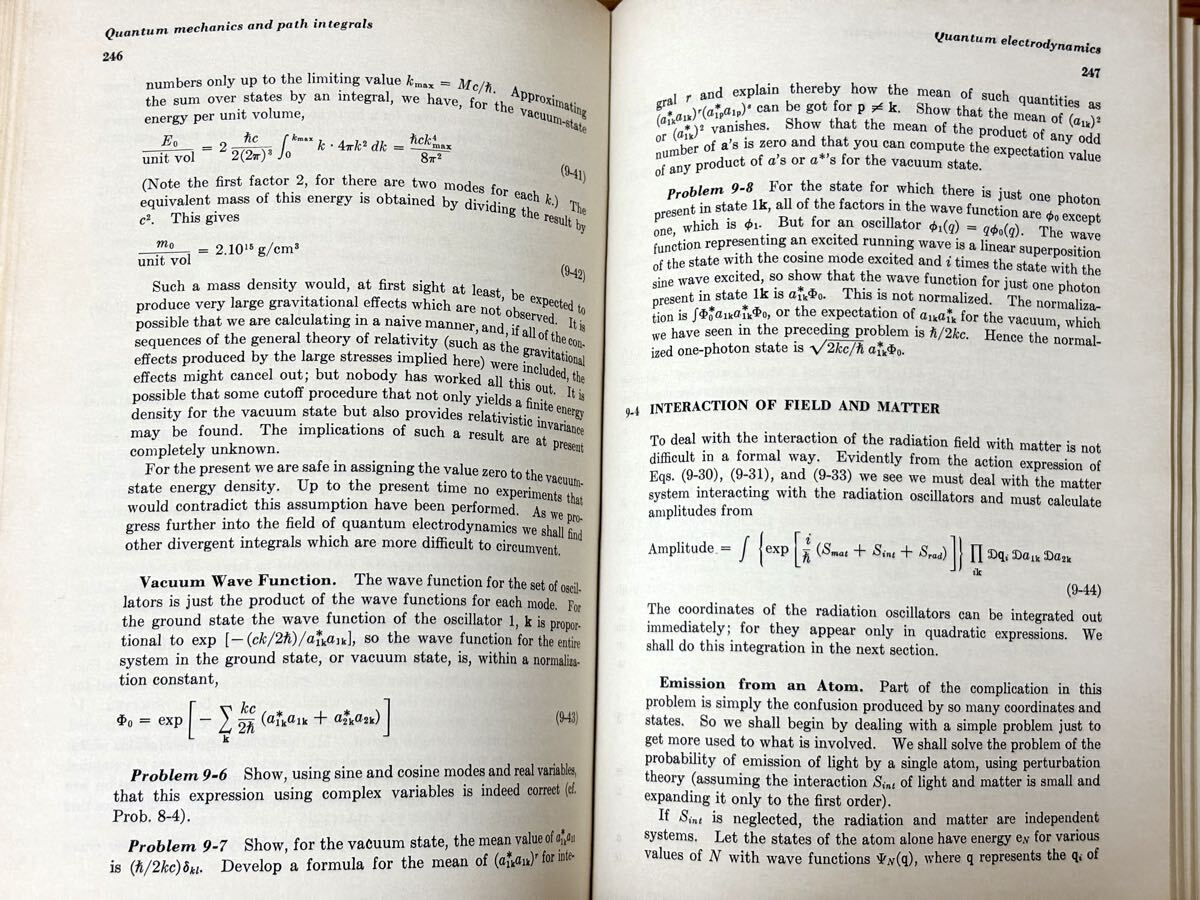
Richard P. Feynman と Albert R. Hibbs
『Quantum Mechanics and Path Integrals』
書き込み線引きマーカー引き押印等見当たりません。
【本書の特徴】
量子力学への経路積分アプローチの根底にある物理学的・数学的概念は、R.P.ファインマンがプリンストン大学の大学院生時代に初めて開発したものです。ただし、本書で述べるようなより発展したアイデアは、数年後になってようやく完成されたものでした。初期の研究では、電子の無限自己エネルギー問題への関心が中心にあり、この研究過程で「最小作用の原理」に基づき、進行波と反射波のポテンシャルを半分ずつ用いる手法が発見されました。この原理によって、古典的な電磁気学に現れる無限大に対処することが可能となりました。
その後、問題はこの作用原理を量子力学にも適用し、古典力学がh/2π→0の極限として自然に量子力学から現れるように扱うことになりました。
ファインマンは、従来の古典的アイデア(ラグランジアンやハミルトンの作用素Sなど)と量子力学のふるまいを関連付ける可能性を探りました。あるヨーロッパの物理学者との会話を通じ、ディラックの論文で発想された「ラグランジアンの指数関数の時間積」は、量子力学の波動関数の時間発展における変換関数と類似しているとの認識に至りました。波動関数の異なる時刻における値は、指数関数的関数によって関連付けられるのです。
そこで次に問題となったのは、ディラックの言う「類似」という語の意味であり、ファインマンはこれを「等号」で置き換えられるかどうか追究しました。簡単な分析で、実際にこの指数関数がこの場面で直接使えることが判明しました。
さらに、ラグランジアンの指数を有限時間区間での変換関数として用いることで、全空間変数について積分しなければならないことも明らかになりました。
このアイデアの解説論文の準備の過程で「あらゆる経路上での積分」という概念が発展し、空間座標の積分を体系的かつ明快に行う数学的手法へと進化しました。以降、経路積分が数々の応用へ展開されていきましたが、当時の主要な方向付けはむしろ量子電磁気学でした。実際、この積分法自体は、量子電磁気学における困難の根本的な解決手段とはなりませんでしたが、他の分野では有用性が見出されています。特に、量子電磁気学の法則の表現や、相対論的不変性の扱いなどに活用されています。さらに、他の量子力学的な問題への応用もすでに進展しています。
経路積分の最も劇的な初期応用例は、ラムシフトの導出とそれに伴う定量的困難の解決にあります。この経路積分アプローチは、量子力学の講義に用いられ、特にカリフォルニア工科大学でファインマンとA.R.ヒブスが講義用教案の構築を行い、後にその内容を本書としてまとめました。以降、研究の質が高まるにつれ、ファインマンの量子力学教育の姿勢も初期の経路積分アプローチからやや離れ、より一般的な量子力学問題の解決へと深化しました。現在は作用素技法がより深遠かつ一般的な解法となっていますが、経路積分法は依然として量子力学の直観的理解において有益です。









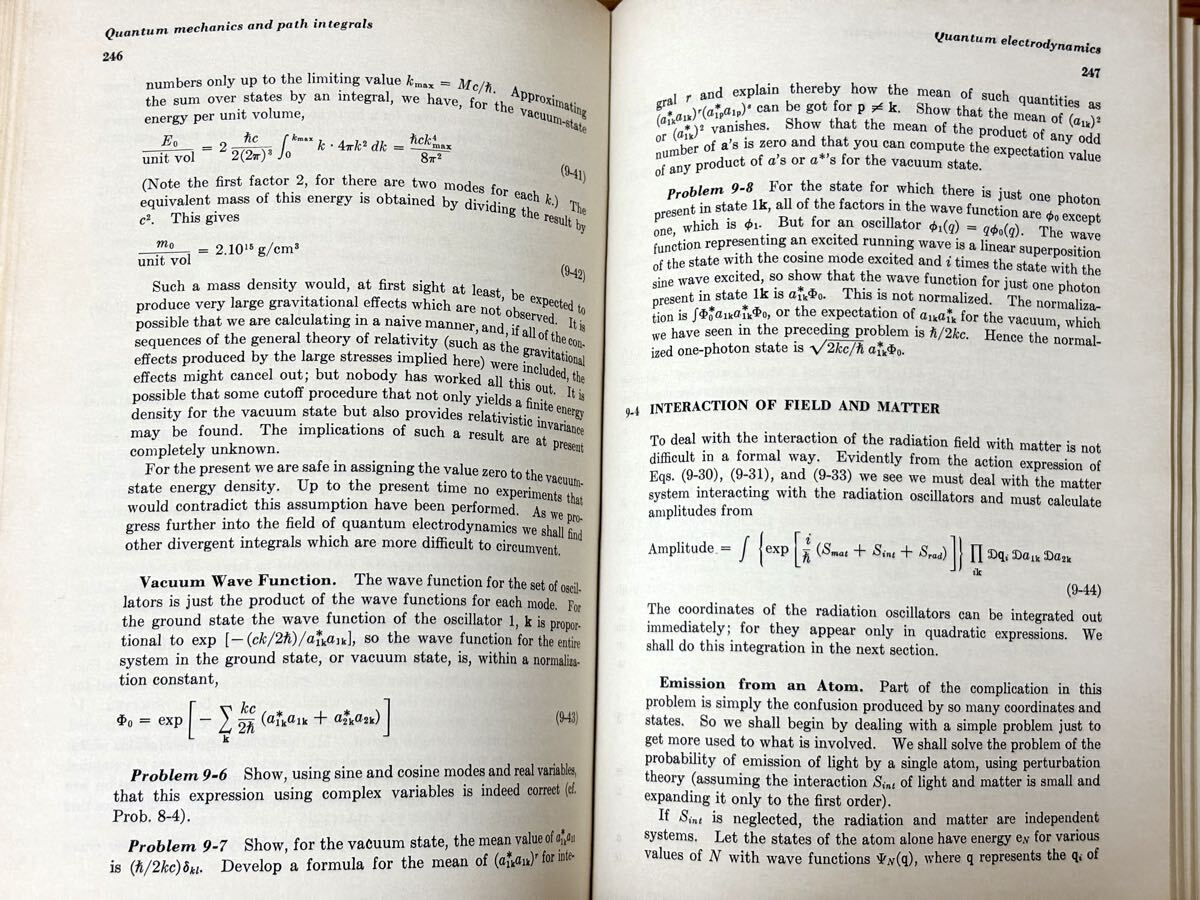 Richard P. Feynman と Albert R. Hibbs
Richard P. Feynman と Albert R. Hibbs