太陽シリーズ 仏の美と心 IV 密教と聖なる山。
本巻ではまず、仏教とインドの民間宗教の習合から生まれた密教の、日本における多彩な芸術的展開を取り上げる。
難解な教義を視覚的に説明する曼荼羅、神秘的で人間離れした外観を持つ尊像など、平安時代の人々を驚かせ、興味をそそったに違いない。このセクションでは、曼荼羅はもちろんのこと、密教絵画、密教彫刻、密教法具に至るまで、密教の芸術作品について考察する。また、曼荼羅の解釈を助ける解説図も掲載した。
また、平安時代中期に修験道が発展する過程で、仏教、特に密教と道教、日本固有の山岳信仰などが融合したことも本書のテーマである。
神護寺、教王護国寺などの収蔵庫に現存する最古の様式化された曼荼羅を、両界曼荼羅に始まり、仏眼曼荼羅、大仏頂曼荼羅、星曼荼羅、童子経曼荼羅など、多数紹介する。(11~32ページ)
表現・本質・統一の世界を象徴する金剛界曼荼羅と、変化・多義性の内面的・心理的世界を象徴する胎蔵界曼荼羅が一対となり、両界曼荼羅と呼ばれる。この一対の曼荼羅は、真言密教の最も基本的な教義を視覚的に示しています。また、これらの重要なコスモグラフィーを説明する図表も用意した。(16~19ページ)
その色彩から青不動と呼ばれる正蓮院の不動明王と二童子のように、怒りに満ちた恐ろしい表情の聖像を描いた密教絵画や、三頭の白象に座した普賢延命や孔雀が蛇を貪る姿の孔雀明王など、幻想的な姿を描いた密教絵画を紹介する(33~45頁)。
様々な形で神を具現化することは密教の教義の本質であり、これに合わせて、慈悲深い知恵を讃える金剛峯寺の大日如来(ヴァイローチャナ)に始まる、奇妙で異形の姿や怒りの表情をした尊像を描く密教彫刻も紹介する。(46~59ページ)。
真言宗の修法や儀式で使われる法具など、密教の儀式や修行で使われるさまざまなものを写真に収めた。(60~70ページ)
最後に、大峯山での修行、そして密教の教えの延長ともいえる山伏全般を取り上げたフォトエッセイをお届けする。
(91~126ページ)
巻末解説に、後七日御修法の詳しい解説(一般に公開できる範囲)なども含めて、
仏教美術史家、仏教学者、仏教美術研究家、宗教学者などの第一人者による解説や寄稿により、
難解な密教美術について一般の美術愛好家にもわかりやすく、踏み込んだ内容も解説して主要な密教美術作品をみていく内容の、大変貴重な資料本です。
【目次】より 小見出しも一部紹介します
巻頭対談
仏の美と心 清水公照(207、208世東大寺管長)・佐多稲子
人間性と五欲 生と死のすがた 心の問題と文学 私の仏縁のこと 自然への畏怖と信仰 曼荼羅の世界と大欲清浄 忿怒相と慈悲相 生死一枚の舟
●カラー
密教と聖なる山 写真:入江泰吉・矢沢邑一・西川孟・矢野建彦ほか
「深遠なる理想図」—曼荼羅 解説:有賀祥隆
両界曼荼羅 解説:有賀祥隆
空海の請来本現図曼荼羅 現図胎蔵曼荼羅の構成 現図金剛界曼荼羅の構成
異形の画像 解説:有賀祥隆
忿怒と慈悲の尊像 解説:松浦正昭
密教法具 解説:関根俊一
修験 聖なる大峯山をゆく 写真:矢野建彦 イラスト 藤田道世
●本文
ほとけと私 第四話 ほとけたち 三枝充悳
仏像をめぐって 仏身論 ブッダとほとけ、ボサツ ほとけたち ボサツほか おわりに
密教画断章 曼荼羅と不動尊と十二天のことなど 有賀祥隆
はじめに 密教画の請来 両界曼荼羅 不動尊 十二天 おわりに
平安初期の密教彫像 松浦正昭
競いたつ二大密教 真言密教教理の空間と彫像表現 濃密な色彩の映発 天台密教彫像の特質
密教工芸への誘い―密教法具を中心として 関根俊一
修験道―その歴史と修行 宮家準
修験道の歴史 古代の山岳信仰 修験道の成立 近世の修験道 近代の修験道
修験道の修業 カラー写真参照 山上ヶ岳の修業 奥駈と深仙灌頂 南奥駈と熊野三山の祭
大峯山女人禁制雑記 嵯峨崎司朗
真言最極の秘法 後七日御修法について 藤井竜心
密教とは 法身仏とは 御修法 その後の変遷 明治以降 御修法の道場について 道場の荘厳について 修法について
表紙解説・編集室
日本の古寺2000 (うち中国・四国・九州・沖縄リスト) 高橋秀栄・中尾良信・伊藤宗克・佐藤秀孝
【一部紹介】
密教画断章 有賀祥隆
はじめに
奈良時代のいきづまった律令政治と安逸になれた仏教の刷新を計るために平安遷都が行われ、新しい平安時代が始まる。新しい時代にふさわしい新しい仏教として求められたのが密教であった。この密教の深遠な教理からつくりだされた絵画は密教画としていままでに目にしなかった曼荼羅であり、忿怒尊であり、天部の諸尊であった。特に平安前期の密教画は原初的な色あいの強いもので、当時の人々にいいしれぬ驚異と官能の美しさを与えたことは想像にかたくない。ここに新しい密教画のうち、その特色をよく示す両界曼荼羅、不動尊および十二天について図像や表現描写のことも含め、日頃感じていることを折り込みながら述べてみたいと思う。
ほか
真言最極の秘法 後七日御修法(ごしちにちみしほ)について 藤井竜心
(前略)真言密教では、この理論的体系を教相といい、実践的体系を事相と称している。そして、殊に事相に関することは、師資相承を重んずるのである。今日、数多くの伝えられている諸仏、諸尊に対する修法、行規のなかで、真言密教の大法であり、秘法として、大師以来絶ゆることなく、つとめられているのが、宮中真言院後七日御修法である。
ほか
【掲載作品およびカラー写真】一部紹介
両界曼荼羅図 伝真言院曼荼羅 教王護国寺/東寺
両界曼荼羅図 高雄曼荼羅 神護寺
両界曼荼羅図 四天王寺
金剛界八十一尊曼荼羅図 根津美術館
両界曼荼羅図 敷曼荼羅 教王護国寺 東寺
両界曼荼羅図 厨子入 奈良国立博物館
仏眼曼荼羅図 神光院
大仏頂曼荼羅図 奈良国立博物館
星曼荼羅図 法隆寺
童子経曼荼羅図 智積院
金剛薩菩薩図像 東京藝術大学
普賢延命菩薩像 松尾寺
金剛吼菩薩像 五大力吼菩薩のうち 有志八幡講十八箇院
不動明王二童子像 青不動 青蓮院
不動尊像 甚目寺
降三世明王像・軍荼利明王像 五大尊像のうち 来振寺
孔雀明王像 東京国立博物館
愛染明王像 個人蔵
水天像・風天像 十二天像のうち 京都国立博物館
梵天像・帝釈天像 十二天像のうち 聖衆来迎寺
月天像 十二天像のうち 西大寺
大日如来坐像 金剛峯寺
大日如来坐像 向源寺
孔雀明王像 金剛峯寺
愛染明王坐像 西大寺
愛染明王坐像 奈良国立博物館
不動明王坐像 教王護国寺 東寺
五智如来像 五体のうち 安祥寺
五大虚空蔵菩薩坐像 神護寺
五大明王像 奈良国立博物館
八大童子像 矜羯羅童子・制迦童子
密教法具 金剛錫杖 善通寺
金銅透彫舎利塔 西大寺
金剛三昧耶形五鈷鈴 護国寺
金銅八角輪宝 金剛三昧院
金銅密教法具 八口のうち 五鈷鈴 独鈷鈴/四天王鈴 独鈷杵 五鈷杵 三鈷杵
屏風本尊 竜光院
宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子函 仁和寺
輪宝羯磨文戒体箱 醍醐寺
倶利伽羅蒔絵経箱 奥院
修験聖なる大峯山をゆく
修験僧の山伏姿
大峯山の戸開式
大峯山寺内陣
洞川龍泉寺の水行場で身を清める
大峯山寺参詣後の総礼
山上ヶ岳への登拝
西ののぞき
裏行場胎内くぐり 護摩の岩屋
稚児泊
内侍おとし
八経ヶ岳に到着
釈迦ヶ岳山頂東南院奥駆けの柴燈護摩
大日ヶ岳の岩場
前鬼裏行場三重の滝でのはげしい修行
聖護院が行う深仙灌頂伝法会
山伏たち
笠捨山
花折塚
宝冠の辻に進む
宝冠の森で護摩を焚く
熊野本宮の砂利道を進み参拝
音無川にて川を拝する
熊野川に沿い新宮速玉大社を経て那智の滝を拝する
新宮神倉神社の御燈祭
那智の火祭
本宮例大祭
新宮速玉大社の御船祭の早船
この海の彼方に観音の補陀落浄土があるという
【著者について】
<解説・寄稿>
有賀祥隆 仏教美術史学者、東北大学名誉教授。文化財保護委員会事務局美術工芸課文部技官、奈良国立博物館学芸課普及室長、同仏教美術資料研究センター資料管理研究室長、文化庁文化財保護部美術工芸課文化財調査官、同主任文化財調査官、東北大学文学部教授、名誉教授、東京芸術大学客員教授、美術史学会代表委員を歴任。
<寄稿>
藤井竜心 仏教学者、僧侶。種智院大学教授。真言宗智山派管長。智積院65世能化。専門は密教学。
松浦正昭 美術史家・仏教彫刻史研究者。奈良国立博物館学芸課教育普及室長、仏教美術資料研究センター仏教美術研究室長、東京国立博物館に上席研究員文化庁美術学芸課美術館・博物館主任文化財調査官、富山大学芸術文化学部教授、放送大学客員教授などを歴任。。
宮家準 日本の宗教学者。専門は修験道研究。慶應義塾大学名誉教授。2012年宗教法人修験道管長、法首およびその総本山五流尊瀧院第37代住職。日本学術会議会員。
関根俊一 慶應義塾大学大学院文学研究科哲学専攻(美学美術史)修士課程修了。奈良国立博物館学芸課研究員、普及室長を経て、現在帝塚山大学人文学部教授。 著書に、『仏・菩薩と堂内の荘厳』(日本の美術281号 至文堂)、『梵天・帝釈天』(同375号)、『山岳信仰の美術 日光』(同467号)、『古神宝』(同511号)
ほか
THE SUN Series No. 36
Beauty and Mind of the Buddha IV
Esoteric Buddhism and the Holy Mountain
In this volume we will first of all deal with the variegated artistic development in Japan of Esoteric Buddhism which emerged from the confluence of Buddhism with Indian folk religion.
The mandalas which visually explicate the recondite doctrines, the sacred images which had such a strange and mystically inhuman appearance, and other trappings certainly must have surprised and intrigued the people of the Heian period. In this section we consider artistic works of esoteric Buddhism including, naturally, mandalas but also extending through painting, sculpture and ritual implements. We have also included explanatory charts to aid the reader in interpreting the mandalas.
Another theme of this volume is the amalgamation of Buddhism, especially Esoteric Buddhism, with Taoism, indigenous Japanese mountain worship, and other belief systems which resulted in the development of Shugendo (mountain asceticism) in the middle of the Heian Period, We have collected a large number of color photographs to give the reader a concrete feel for the festivals and ascetic regimen in the Omine mountains in Yamato which became the major training center for mountain ascetics.
We introduce a number of the oldest extant stylized cosmographic mandalas from the storehouses of Jingoji, Kyoo Gokokuji, and elsewhere begining with the Mandala of Two Worlds, and including the Buddha Eye Mandala, the Daibutcho Mandala, the Star Mandala, the Children's Sutra Mandala. (Pp. 11~32)
Together the Kongokai Mandala (World of the Diamond) which symbolizes the world of expression, essence, and unity and the Taizokai Mandala (World of the Womb) which represents the inner or psychological world of change and multiplicity form a pair which are called Mandala of the Two Worlds. This mandala pair visually presents the most fundamental esoteric doctrines of Shingon Buddhism. We have also provided a chart to explain these import-ant cosmographs. (Pp. 16~19)
We introduce a number of esoteric Buddhist paintings which depict sacred figures with angry and terrifying countenances such as the Fudo Myoo and Two Children from Shorenin, known as the Blue Fudo because of the coloration of the central figure, and those which present fantastical figures such as that of Fugen Enmei (Samantabhadra of Long Life) seated upon a three-headed white elephant or Kujaku Myoo appearing as a peacock devouring a snake. (Pp. 33~45)
Embodiment of the divine in a variety of forms is the essence of the esoteric doctrine and in keeping with this we introduce esoteric sculpture which also depicts sacred images asuming strange and monstrous forms or wearing expressions of anger beginning with the Dainichi Nyorai (Variocana) of Kongobuji which celebrates compasionate wisdom. (Pp. 46~59)
We have included photographs of a variety of objects used in Eso-teric Buddhist ritual and practice such as implements used in Shin-gon prayer services and burnt-offering ceremonies. (Pp. 60~70)
? Finally we provide a photo essay covering the practices of Mt.
Omine and envious and the mountain ascetics in general which can be seen as an extention of esoteric teachings. (Pp. 91~126)
COVER: a part of "Ichijikinrin Mandala"
EDITOR: Shinji SATO









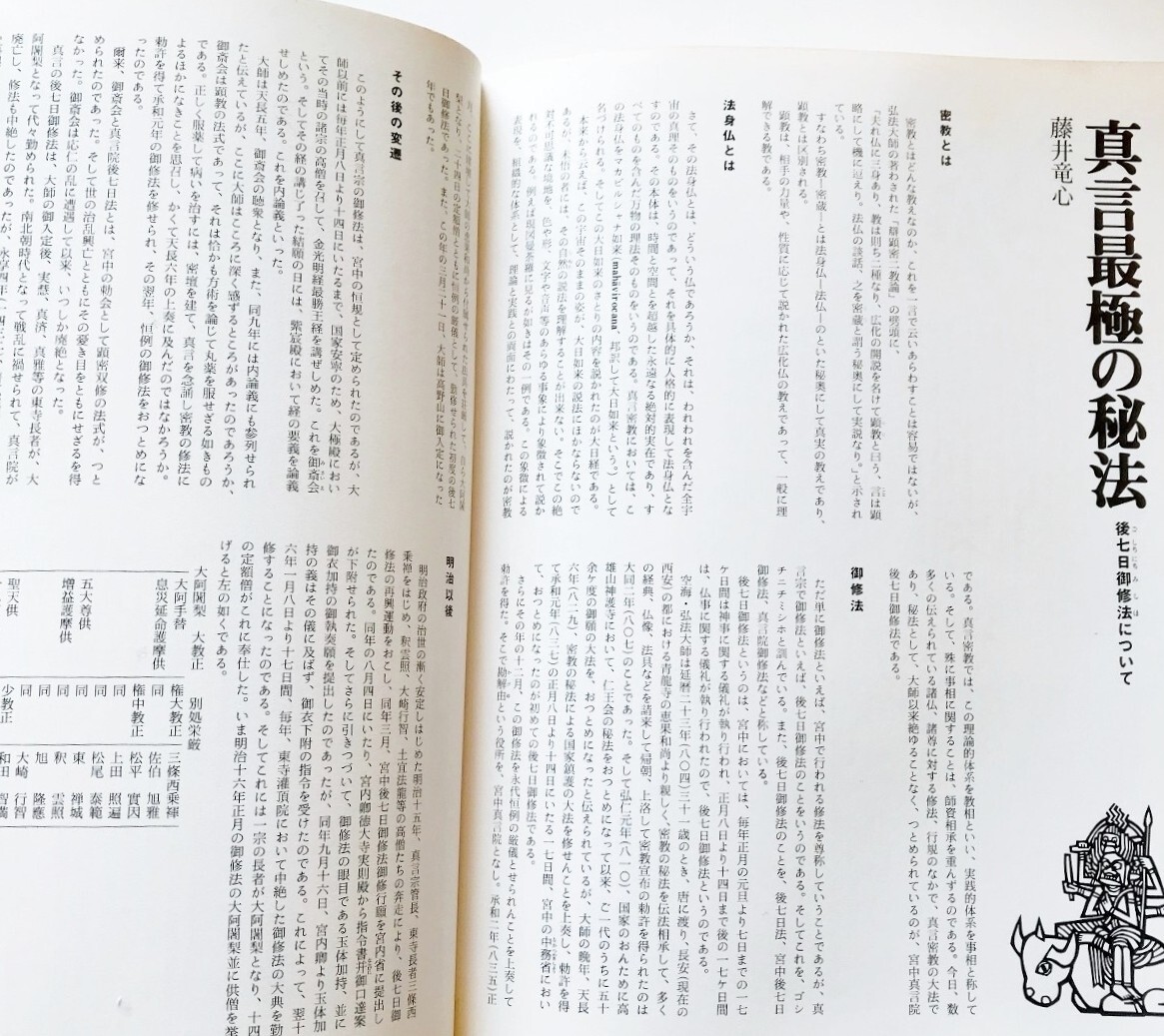 ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。
ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。



